トランプ関税が日本に与える影響とは?中小企業経営者が知っておくべきリスクと対応策
公開日:2025年7月14日
その他

2025年1月に第2次トランプ政権が発足して以来、特に大きな話題となっているのが「トランプ関税」です。アメリカにおける関税の強化が貿易に与える影響は大きく、さまざまな国で経済や社会情勢の混乱が懸念されています。
今回はトランプ関税が日本にどのような影響を与えるのか、これまでの経緯も含めてわかりやすく解説します。その上で、個々の中小企業はどのようにリスクと向き合っていくべきなのか、基本的な対応策を確認していきましょう。
関税とは

「関税」とは、外国からの輸入品に対して、輸入者が自国に納めなければならない税金を指します。日本における関税の納税者は、外国から日本へ商品を輸入した個人や企業であり、日本国政府に対して納めます。
関税の基本的な目的は、「税収の増加」と「自国産業の保護」の2つです。関税は輸入された商品の量や金額に紐づいて発生するため、輸入の増加とともに税収も増えていきます。
また、通常であれば輸入品には関税分のコストが上乗せされるため、自国で生産された商品と比べると、価格競争では不利になります。そのため結果として、自国の産業を守るというのが関税のもう一つの役割です。
関税の実施は、基本的にこのどちらかあるいは両方を目的に行われますが、後述する「報復関税」のように国際交渉時のカードとして切られるケースもあります。
トランプ関税とは

「トランプ関税」とは、第2次トランプ政権(2025年1月20日~)の発足後に進められている一連の関税措置の総称です。主な目的はアメリカ経済の保護であり、関税の引上げによって輸入の抑制と輸出の増加を実現し、国内の産業活性化につなげることが狙いとされています。
世界第一の経済大国であるアメリカの関税強化は、国際貿易に与える影響が大きく、世界経済の混乱や株価の乱高下等が強く懸念されています。
トランプ関税の4つのポイント
トランプ関税はさまざまな政策の総称であるため、まずは全体像を丁寧に把握していく必要があります。ここでは、トランプ関税を以下の4つのポイントに分け、一つずつ整理していきましょう。
・10%の「ベースライン関税」
・特定の国を対象とした関税
・鉄鋼・アルミニウム製品を対象とした「品目別関税」
・対輸出における関税率や非関税障壁等を考慮して決められる「相互関税」
ベースライン関税
ベースライン関税とは、すべての国・地域を対象とした一律の関税のことです。アメリカでは4月5日から、すべての国・地域から輸入されるほぼすべての品目に、「一律10%」のベースライン関税が課されています。
特定の国への関税
特定の国への関税とは、中国・カナダ・メキシコの3ヵ国を対象とした追加関税のことです。トランプ政権の樹立後、ベースライン関税が適用される前の段階で、まず着手されたのが上記3ヵ国からの輸入品への追加関税です。
この3ヵ国への追加関税については、国際緊急経済権限法(IEEPA)が根拠法となっています。国際緊急経済権限法とは、アメリカの安全保障や外交政策に対する異例かつ重大な脅威に関して、国家緊急事態の宣言に基づいて大統領に権限を与える仕組みです。
今回の追加関税は、不法移民や合成麻薬フェンタニルの流入を理由とする国家緊急事態の宣言に伴って発動したものです。当初、中国は20%、メキシコ25%、カナダ25%(エネルギー関連は10%)とされていましたが、中国に対する税率(後述の相互関税を含む)はその後34%で落ち着いています。
また、メキシコ、カナダについては、一部の輸入品の関税を免除する救済措置が取られています。
品目別関税
品目別関税とは、特定の品目に対して追加で課される関税のことです。具体的には自動車や自動車部品、鉄鋼・アルミニウム製品等が対象となっています。また、木材、半導体、医薬品、重要鉱物、民間航空機(同部品)等も、輸入に関する調査が行われており、今後は追加関税が発動される可能性があると考えられています。
相互関税
相互関税とは、貿易相手国との関税負担等を調整する目的で設けられる関税のことです。トランプ関税においては、アメリカにとって貿易赤字額が大きいとされる57ヵ国・地域に対して、ベースライン関税をそれぞれ設定した税率まで引き上げる上乗せ関税率が課されました。例えば、EUに対しては20%、中国に対しては34%、東南アジアのラオスやベトナム、ミャンマー等に対しては40%を超える関税が設定されています。
日本に対しても24%の相互関税が設けられており、日本経済への大きな影響が懸念されています。ただし、後述するように引上げ後の相互関税率は時限的に停止されており、2025年6月現在では一律10%のベースライン関税のみ適用されている状態です。
トランプ関税の一連の流れ
トランプ関税は、国際情勢の変化に伴って流動的な動きを見せており、今後もさまざまな変動が予想されています。そのため、今後の見通しを立てる上では、現状だけでなく経緯も丁寧におさえておく必要があります。
ここでは、2025年6月時点までの流れについて、時系列で見ていきましょう。
国別関税、ベースライン関税、相互関税の流れ
まずは、前述のように第2次トランプ政権の発足後間もない2、3月に、中国・カナダ・メキシコへの追加関税が適用されました。カナダ・メキシコへの追加関税は3月4日まで延期されていたものの、最終的には発動される運びとなりました。
それに対して、カナダ・メキシコの両国では、報復関税や非関税措置が検討されているのが現状です。中国に対しては2月4日に10%、3月4日には20%と段階的に追加関税が適用されました。
その後、中国とは報復関税合戦が行われ、一時は追加関税と合わせて145%までの関税が適用されていました。しかし、スイスで行われた米中経済・貿易協議を受け、5月14日以降は34%に落ち着いています。
また、34%のうち24%は90日間の停止措置が設けられたため、2025年6月時点で実際に適用されているのは10%です。なお、カナダ・メキシコについては相互関税が適用されていません。
その間、ベースライン関税は4月5日から発動されています。また、相互関税の対象となっている57ヵ国・地域については、中国と同様に90日間の停止措置が設けられており、7月9日の午前0時1分まではベースライン関税である10%が適用されます。
品目別関税の流れ
品目別関税については、第1次トランプ政権のころから鉄鋼製品・アルミ製品に対して導入されていました。第2次トランプ政権においては、その品目別関税がさらに強化された格好です。
まず、3月12日にアルミ製品の追加関税率が10%から25%に引き上げられ、それとともにこれまで適用されていた例外措置が撤廃となりました。日本に対しても、従来は例外として鉄鋼の関税割当制度(一定量までの追加関税を免除する制度)が設けられていましたが、3月12日のタイミングで撤廃されています。
さらに、4月4日には、それまで適用対象外であったアルミ缶と缶ビール(アルミ缶の部分のみ)も関税対象に追加されました。その後、6月4日には鉄鋼製品・鉄鋼派生品、アルミ製品・アルミ派生品に50%の追加課税が適用されています。
自動車については、4月3日に乗用車・小型トラックに対して25%の追加関税が課されると、5月3日には自動車部品(エンジン・エンジン部品、トランスミッション、パワートレイン部品、電子部品等)にも25%の追加関税が適用されました。
トランプ関税が実行された背景

トランプ関税が実行された背景には、政権の土台となっている「自国第一主義」が関係していると考えられます。関税の強化によって、アメリカの産業を守り、経済を活性化するというのが主な狙いと言えます。
また、品目別関税については、米国経済に生じた格差や不平等を解消するためとの見方も強いです。自動車やアルミニウムの関税強化は、アメリカ国内における製造業の優位性を守る働きがあるため、ブルーカラーワーカーに募った不満を解消するために行われたと考えるのも自然です。
トランプ関税が与える日本経済への影響

それでは、トランプ関税は実際に日本経済へどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、懸念される影響を4つのポイントに分けて見ていきましょう。
対米・対中輸出の減少リスク
日本にとって、アメリカと中国は最大の輸出相手国です。過去20年以上にわたって、アメリカと中国が輸出総額の1位と2位を独占しており、日本にとって重要な貿易相手であることは明らかです。
アメリカで関税が強化されれば、輸出先での価格競争力が低下するため、日本の輸出には大きな悪影響をおよぼす可能性があります。さらに、関税の強化に伴うアメリカ国内での価格高騰・インフレ進行に伴い、消費そのものの低迷リスクも指摘されています。
その結果、対アメリカの輸出減少につながるリスクは十分にあると言えるでしょう。また、もう一つの輸出相手国である中国でも対アメリカでの輸出の減少が見込まれており、景気の悪化リスクが懸念されます。
中国での景気が悪化すれば、日本からの輸入減少につながる可能性もあり、日本にとってはさらなる輸出減に発展する恐れがあります。
サプライチェーンが抱えるリスクや、サプライヤーとして取り組むべき事項について解説しています。
株式・為替相場の急変動リスク
トランプ大統領の選挙公約の一つには「所得減税の恒久化」が挙げられており、大きな話題を集めました。関税によって増えた税収は、所得減税の財源に充てられると説明されており、場合によっては大規模な減税が行われる可能性もあります。
アメリカの景気が回復すれば、金利引上げによって、ドル高円安が進む可能性が高まります。反対に、関税による価格高騰で米国内消費が冷え込み、景気が悪化すれば、ドル安円高を招く可能性もあるでしょう。
このように、トランプ関税にまつわる一連の動きは、為替や株式相場を急変動させるリスクもはらんでいます。その結果、日本においては、輸出のみならず輸入にも少なからず影響が生まれると考えられます。
倒産件数の増加リスク
株式会社帝国データバンクの調査結果によれば、トランプ関税の影響を受ける企業は、およそ1万3,000社と想定されています。さらに、倒産件数も従来予想より3%程度増加すると試算されており、企業経営への影響も懸念されます。
想定される3つのシナリオ
相互関税の停止措置が適用されている現在(2025年6月時点)においては、アメリカの動きによって3パターンのシナリオが想定されています。まず、帝国データバンクにおける当初の予想では、トランプ関税が実行されなかった場合、実質GDP成長率1.2%、国内倒産件数10,235件と想定されていました。
シナリオ1として「相互関税10%が予定通り解除」され、7月に24%へ引き上げられた場合、実質GDP成長率は0.7%(-0.5ポイント)、国内倒産件数は10,574件(+3.3%)と想定されています。
また、シナリオ2としてこのまま「相互関税10%が適用され続ける」場合、実質GDP成長率は0.9%(従来予想より-0.3ポイント)、国内倒産件数は10,489件(従来予想より+2.5%)と試算されています。
さらに、シナリオ3では「相互関税24%が継続」されていた場合、実質GDP成長率は0.7%(-0.5ポイント)、国内倒産件数は10,687件(+4.4%)との結果も試算されました。
このように、いずれにおいても、トランプ関税はGDPや倒産件数にネガティブな影響を与えると考えられています。
自動車・機械製造業への影響
日本国内において、特に大きな影響を受ける業界は、品目別関税の対象となっている自動車や機械等の製造業です。ただし、日本における自動車・自動車部品の輸出額は、毎年全輸出の30%以上の主要なウェイトを占めることから、結果として幅広い産業へ影響をおよぼす恐れがあります。
中小企業における対応策

これまで見てきたように、トランプ関税は日本全体に大きな影響を与える施策と言えます。リスクの度合いは業界や業種によっても異なりますが、中小企業が影響を最小限に抑えるには、ビジネスモデルの転換も踏まえた大幅な対策が必要になるケースもあるでしょう。
ここでは、中小企業における基本的な対応策をご紹介します。
輸出先・輸入元の拡大・分散
現在、対米・対中の輸出が事業の中心となっている企業では、取引先の拡大がリスク回避につながります。アジア各国やEUも踏まえた輸出先の拡大を行い、リスクを分散させる方法を探ることが重要な取組となるでしょう。
一方、世界各国の景気や経済状況も不安定になることから、輸入についても不確実性が高まります。突然の価格高騰や生産停止といったリスクに備えて、原産地の選択肢を広げられるかどうかを検討し、事業プランの柔軟性を高めておくことが大切です。
顧客への価格転嫁とコスト削減
輸出減による利益の低下に備える上では、取り扱う商品・サービスの価格を見直すことも一つのアプローチです。JETROが2025年4月に国内全業種の企業(7,589社)を対象として行った調査によれば、トランプ関税への対応策としてもっとも高い回答を集めたのは顧客への価格転嫁でした。
4割近くの企業が、顧客への価格転嫁を実施・検討していると回答しており、直接的な解決方法として期待されていることがわかります。また、社内におけるコスト削減に取り組むと回答している企業も3割弱あり、複数の手段を織り交ぜた対応が検討されています。
経営の安定性を保つ上では、トランプ関税による影響度合いを考慮しながら、価格の見直しとコストの削減を検討してみることも大切です。
DXの推進、AIの活用
DXの推進による生産性の向上は、トランプ関税による影響を抑える上でも重要な対策となります。例えば、製造業においては「AIを活用した効率的な在庫管理」や「需要予測の精度向上」等が具体的なアプローチとして挙げられます。
また、自社で販売も行っている企業であれば、越境ECの活用による販路の拡大を検討してみるのも良いでしょう。さまざまな国・地域との取引を実現することで、関税による売上への影響をコントロールしやすくなります。
越境ECメリット・デメリット、注意点等について解説しています。
公的支援制度の活用
トランプ関税への対応策としては、公的支援制度を活用するのも有効です。経済産業省の「米国関税対策ワンストップポータル」では、国が主導するさまざまな支援策がまとめられています。
中堅・中小企業との関連性が強いものとしては、「セーフティネット貸付の要件緩和」や、「相談窓口の拡大」、「日本貿易保険(NEXI)による運転資金調達」等の支援が挙げられます。セーフティネット貸付は、本来売上高の減少率等の数値要件が設けられていますが、自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者(自動車業界の事業者に限らない)については、数値要件を満たさなくても利用できるようになっています。
また、日本貿易保険は一般的な関税措置は保険金の支払事由から除外されていますが、トランプ関税によってそれまでの輸出契約が破棄されてしまった場合等は、例外的に保険金支払の対象へ含められました。ここでは、さらに上記以外の支援制度として「ミカタプロジェクト」と「中小企業向け補助金の優先採択」について詳しくご紹介します。
ミカタプロジェクト
ミカタプロジェクトとは、中堅・中小自動車部品サプライヤーに対する支援制度です。もともとは電気自動車で需要が減少してしまう部品の製造を扱う企業等をサポートするために設けられた制度であり、車両の変化に伴う技術適応、事業転換等を推し進める仕組みが整えられています。
具体的には「実地研修・セミナー」「個別相談」「専門家の派遣」「設備投資補助」の4つの柱で、中堅・中小の自動車部品サプライヤーを支えます。セミナーや相談窓口は基本無料で利用できるほか、専門家の派遣も5回までは無料で活用可能です。
トランプ関税を機に事業転換を図る場合等では、ミカタプロジェクトの活用を検討してみるのも有力な策となるでしょう。
中小企業向け補助金の優先採択
トランプ関税によって大きな影響を受ける事業者については、中小企業向けの補助金制度である「ものづくり補助金」や「新事業進出補助金」等の優先採択を受けられる場合があります。「事業が影響を受けているかどうか」は審査によって判断されますが、補助金の活用によって、新事業への展開をめざすのも有効な手段と言えます。
2025年に新設される補助金制度について解説しています。
補助金の申請から入金までの流れについて解説しています。
まとめ
トランプ関税は、日本のみならず国際的な影響をおよぼす重大な施策であり、輸出・輸入の双方に大きな変化をもたらす恐れがあります。特に品目別関税が適用されている自動車・自動車部品やアルミニウム・鉄鋼製品等を扱う企業は、自社の経営を大きく左右する出来事にもなりかねません。
関税に関する施策は世界情勢に応じて細かく変動しているため、まずはトランプ関税の全容を丁寧に押さえ、今後の見通しに活かしていくことが大切です。その上で、自社が直面しているリスクを分析し、公的支援の活用も視野に入れながら、効果的な対応プランを検討しましょう。
【参考情報】
2025年6月20日付 財務省 「わが国の関税制度の概要」
2025年6月4日付 日本貿易振興機構 「米国トランプ政権の関税政策の要旨~相互関税、自動車・同部品、鉄鋼・アルミ、カナダ・メキシコ・中国~」
2025年4月付 経済産業省 「米国関税措置等の世界情勢について」
2022年4月4日付 日本貿易振興機構 「米税関、日本の一部鉄鋼製品に対する関税割り当て導入を4月1日に開始」
2025年5月1日付 公益社団法人日本経済研究センター 「トランプ関税の背景にあるもの:最適関税で迫る国際的な所得移転システムの見直し」
2025年6月20日付 経済産業省 「米国関税対策ワンストップポータル」
2025年4月22日付 日本貿易振興機構 「米国トランプ政権の追加関税に関するクイック・アンケート調査結果-グローバルサプライチェーンに幅広い影響、最新情報への高いニーズ-」
2025年4月28日付 経済産業省 「自動車産業ミカタプロジェクトのページ」
2025年4月1日付 全国中小企業団体中央会 「ものづくり補助金総合サイト」
2025年6月20日付 独立行政法人中小企業基盤整備機構 「新事業進出補助金」
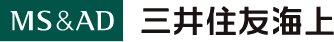

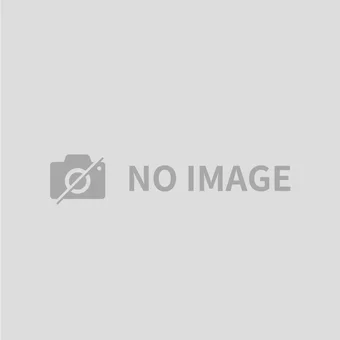
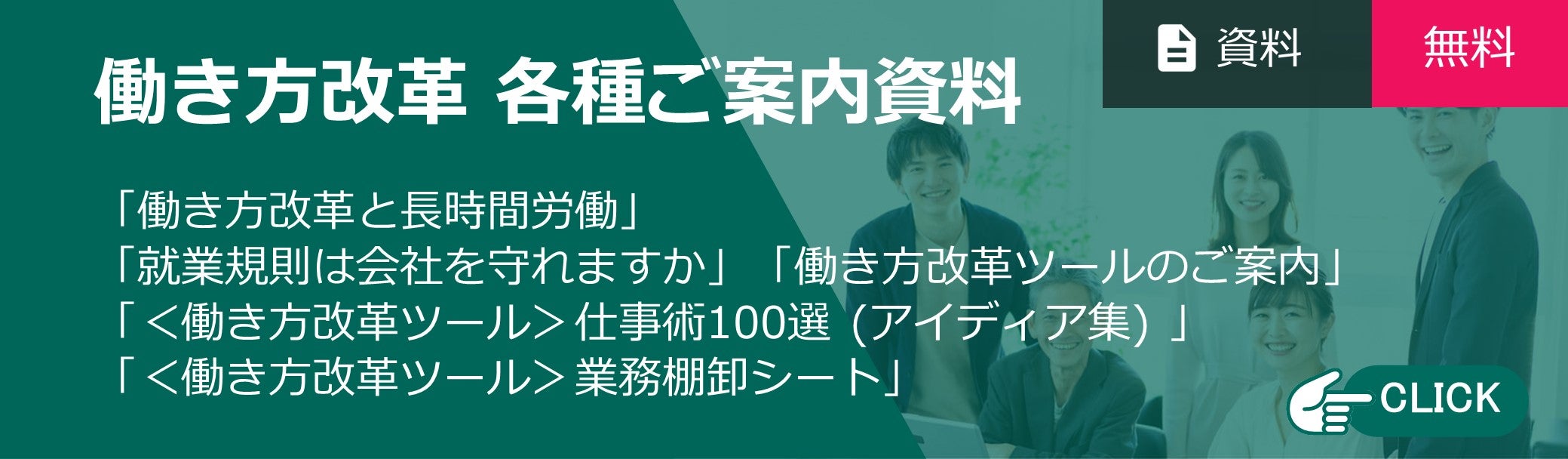

.png)










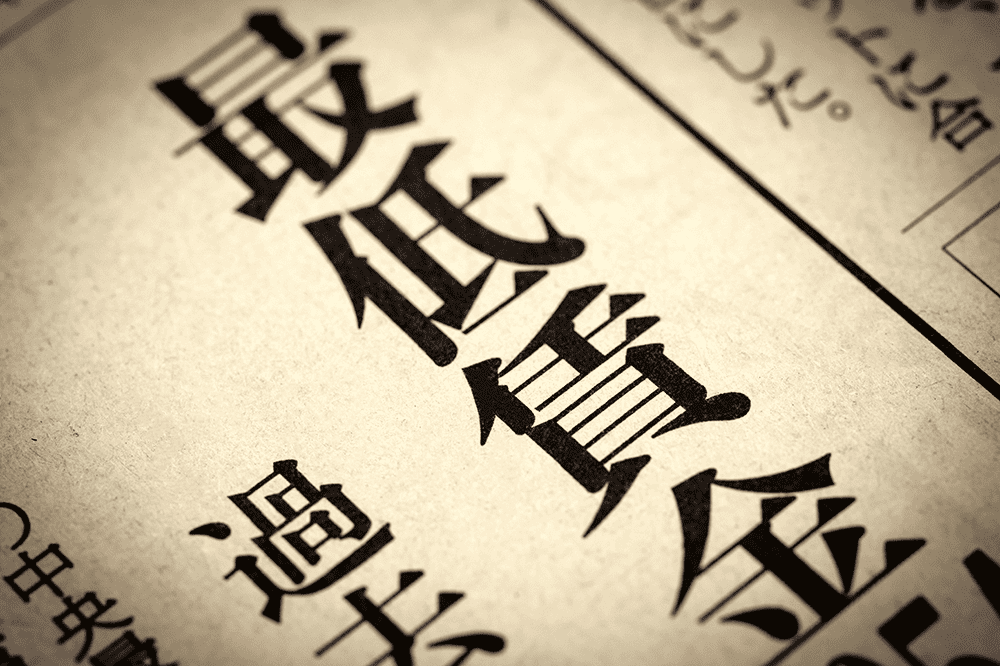

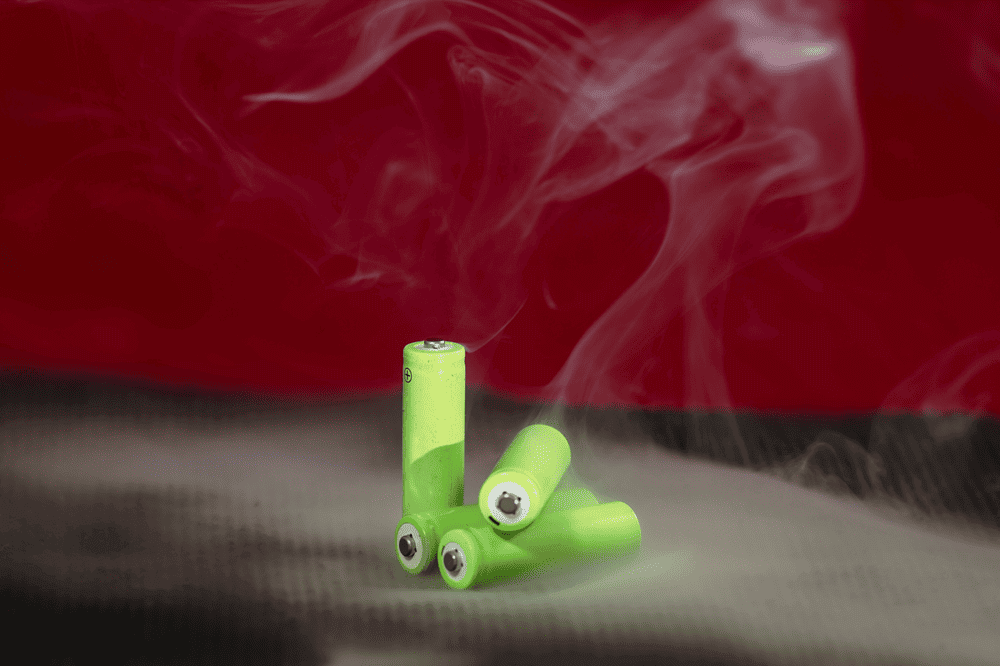
.jpeg)